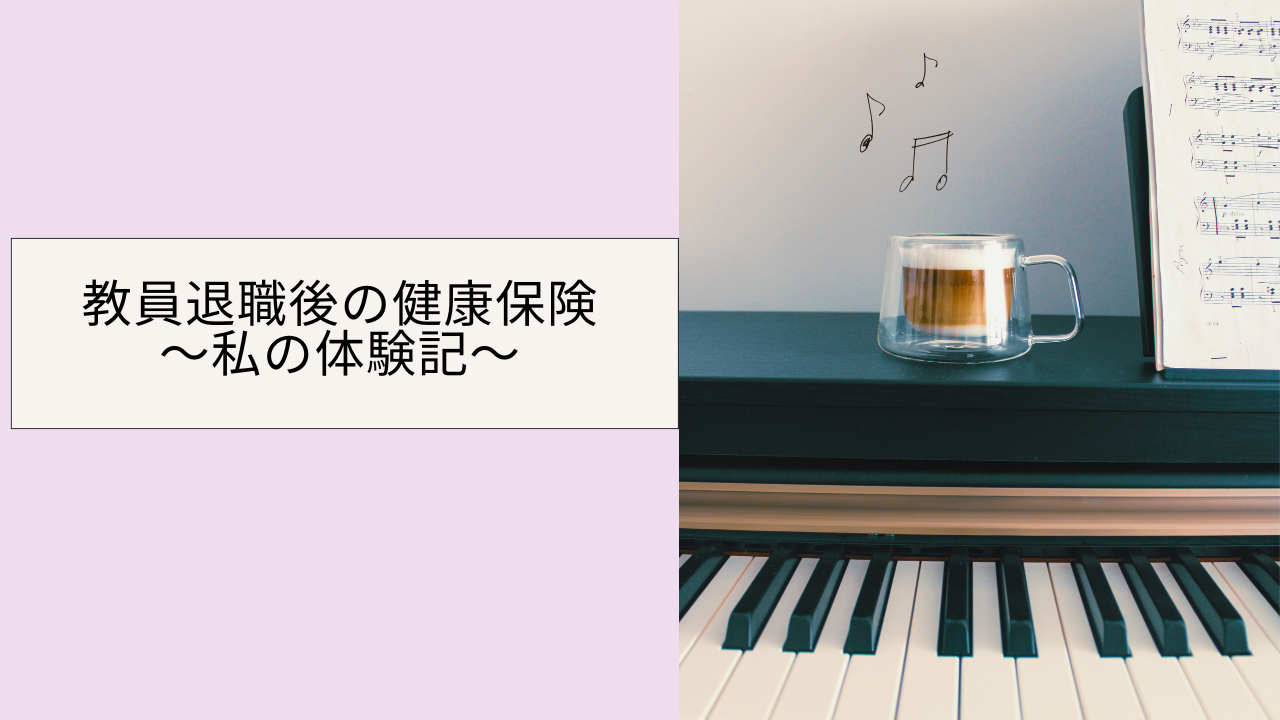「教員を退職したけれど、まず何をすればいいの?」「健康保険ってどうすればいいの?」そんな不安を抱える方に向けて、この記事では教員退職後に必要な手続きや健康保険の選び方
退職後14日以内に必要な手続きや、健康保険の「扶養」「国民健康保険」「任意継続」どれを選ぶべきかについても丁寧に解説します。
教員退職後にすぐ必要な手続きとは?
退職したら、まずは以下の手続きを早めに済ませましょう。中でも健康保険と年金の切り替えは「14日以内」が原則なので注意が必要です。
| 手続き内容 | 期限 | 手続き先 |
|---|---|---|
| 健康保険の切り替え | 14日以内 | 市区町村 or 共済組合 |
| 国民年金の切り替え | 14日以内 | 市区町村役所 |
| 雇用保険(失業保険)の手続き | 離職票到着後 | ハローワーク |
退職後の健康保険の選択肢は3つ
退職後の健康保険には、次の3つの選択肢があります。
- ① 配偶者の扶養に入る
- ② 国民健康保険に加入する
- ③ 共済組合の任意継続を選ぶ
① 配偶者の扶養に入る|保険料はかからないが条件あり
配偶者が会社員・公務員など社会保険加入者であれば、収入条件を満たすことで扶養に入る=保険料が0円で済みます。
ただし、扶養申請に必要な書類や見込み収入の確認などがあり、元職場から書類をもらう場合も。私自身、「退職後も職場とやり取りするのがつらい」と感じ、見送ることにしました。
② 国民健康保険|前年度収入で決まるから高くなる可能性も
市区町村で加入する健康保険。前年度の収入が基準になるため、退職後に無収入でも前年に収入があれば保険料が高額になることがあります。
私の場合、試算では月額5万円前後でした。年収が高かった年の翌年に退職する方は、注意が必要です。
③ 任意継続|共済組合の保険を最長2年間継続できる
これは私が最終的に選んだ方法です。教員の場合、共済組合の保険を最長2年間、自費で継続できる「任意継続」制度
私の自治体では4月10日までに申請しないと加入できない仕組みでした。一度扶養に入ってから任意継続に切り替えることは不可だったので、慎重に判断しました。
結果として、保険料は月4万3000円。国保より安く、扶養に比べると負担はあるけれど、職場とのやり取りを避けられるという安心感がありました。
【体験談】なぜ私は任意継続を選んだのか? 「扶養が一番お得」と頭ではわかっていたものの、どうしても前の職場とやりとりをしたくなかったんです。 「せっかく辞めたのに、また共済組合に連絡して書類を出して…」
そう思うだけで、心が重くなりました。 だから私は、金額だけでなく「気持ちがラク」であることを優先して、任意継続を選びました。
教員退職後は、心にも余裕が持てる選択を 退職後の手続きは、金額や制度の違いだけでなく、自分にとってどんな選択が「安心できるか」がとても大切です。
手続きには期限があるので、事前に情報を集めておくことで、落ち着いて進めることができます。
・教員退職後の手続きと健康保険の選び方
・ 退職後は14日以内の手続きが必要(健康保険・年金)
・ 健康保険の選択肢は「扶養」「国保」「任意継続」
・ 任意継続は制度的にも精神的にもバランスが良い選択肢
・ 金額だけでなく「心の負担の少なさ」も大切に
読んでくださってありがとうございました。この記事が、退職後の不安を少しでも軽くできたなら嬉しいです。