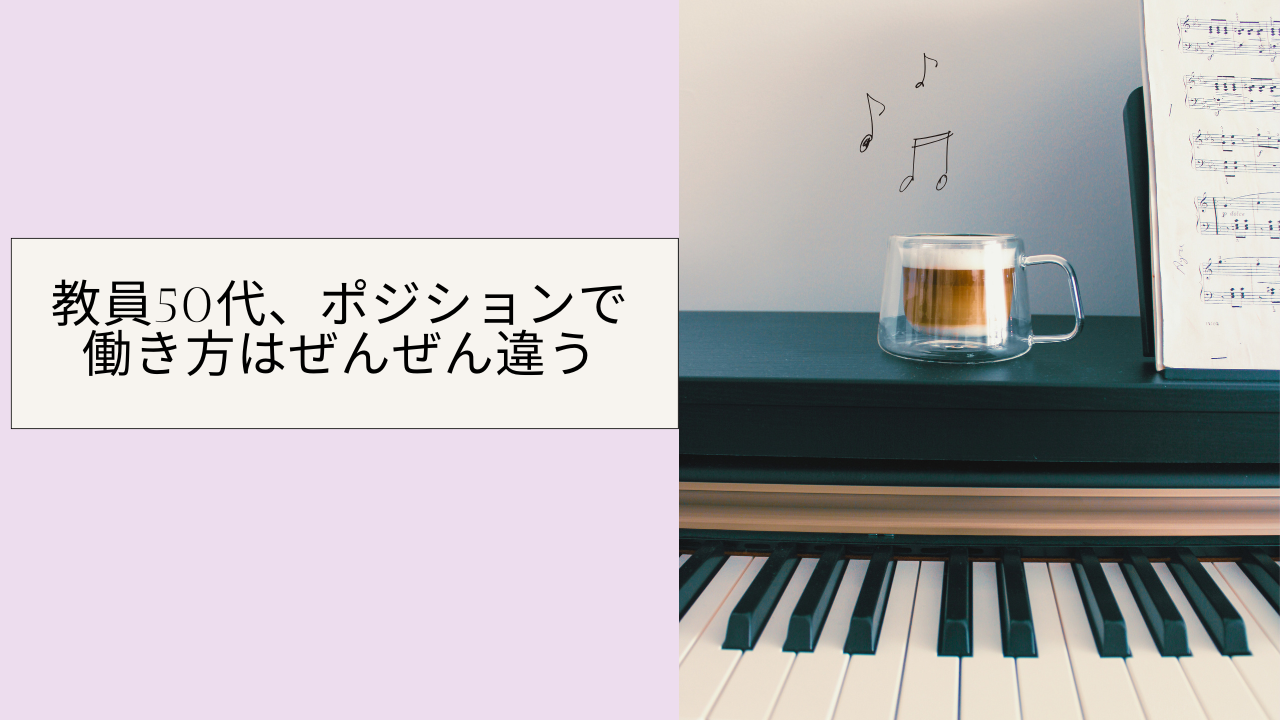「教員は定年まで担任をし続けるのが当たり前」――
かつてはそんな風に思っていました。
でも、50代に差しかかる頃、教員という働き方にはさまざまなルートがあることに気づきました。
私は2025年3月末、定年まであと10年を残して、教員を早期退職しました。20年以上勤めた教職人生のなかで、50代の働き方は大きく分かれていくのを肌で感じてきました。
教員50代、働き方は大きく「4つ」に分かれる
私のまわりでは、50代になると大きく分けて以下のルートに分かれていきました。
① 管理職ルート(副校長・校長)
30代後半~40代で管理職に打診され、そのまま副校長、校長の道へ。
責任も増えるが、意思決定に関われるやりがいも。
→ ただし、心身ともにハードな一面もあり、早期退職した管理職の友人や降格人事を希望して担任に戻った友人も多くいます。
② 行政職ルート(教育委員会など)
学校現場を離れ、行政の立場で教育に関わる。研修運営や制度設計など教員職では味わえない経験ができます。
→ 担任とは違う角度から教育に関われるが、現場とのギャップに戸惑うことも。行政職に異動して良かったという友人はほとんどいなく、激務のために体調を崩す人が多い印象です。よっぽどのステータスが欲しい人には向いているかもしれません。
③ 専門職・加配教員(通級指導、支援学級、教科専科)
担任業務からは外れるが、子どもと深く関われるのと、担任より心理的な負担は圧倒的に少ないように思います。たとえば、算数専科になったら算数ばっかりを1年間授業するので、おのずと算数授業の力量が上がります。
→ 子どもとの関わりの質が変わり、新たなやりがいを感じやすく、人気のポジションです。
④ 学級担任の道を貫く
担任として定年まで勤め上げるルート。教員不足の中、なかなか私の周りで50代で学級担任のままでいれる人は少ないです。
→ 責任の重さや業務量に見合わず、待遇面では報われにくい側面も。
働き方が分かれ始めるのは「40代前半〜半ば」
はっきりルートが分かれたのは40代頃からでした。
自ら意思を示した人もいましたが、多くは校長からの打診や職場の事情で自然に流れていった印象です。
【私のケース】
私は30代後半に管理職への打診を受け、〇〇部長や行政職、主任などを歴任しました。
毎月の手当がつき、担任業務から離れたことで、違う関わり方ができるようになり、新たな楽しさがありました。
一方で、学級担任として直接子どもと接する時間が減る寂しさも感じていました。
教員の働き方は選べる時代に
同じ「教員公務員」という立場でも、役割によって働き方も負担も大きく異なります。
だからこそ、自分に合ったルートを選び、納得感を持って働くことが大切だと私は思います。
定年延長の時代、早期退職という選択肢も
定年延長が言われる中で、定年まで働き続けることがどれほど大変なことかを実感しています。
私の周囲では、50代での早期退職も増えており、その後は講師として非常勤で働く人、まったく別の道に進む人も。
「定年=ゴール」ではなく、自分らしい働き方を見つけること。
それが、これからの教員人生を考える上での大事な視点になると思います。