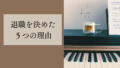私が大学を卒業したころは、いわゆる就職氷河期で、大学4回のときはほとんどの同級生が、黒上下の同じようなリクルートスーツ、同じような靴とかバンに同じような髪形をして、100社前後の入社試験に立ち向かっていました。
今、思えば、それこそがまさに日本の同調圧力を表現している中で、どのような基準で企業にとっての優秀な人材を『内定』としてきたのだろう。
年功序列が崩壊してきて、大学生の間に起業をしたり、卒業後の過ごし方も千差万別になってきているように思うけど、私たち世代は定年が65歳になったとしても、まだまだ会社という組織の枠組みで生き延びられる状況があります。
高学歴、高年収こそが幸せという風潮の中で育ってきたけど、
最近の本屋さんで立ち並ぶ雑誌や書籍の表紙は
「あなたらしく」
「もっとわがままでいい」
「しばられずに生きる」
のような、自分軸で生きることを推奨しているかのようなタイトルをよく目にするようになりました。
少し前までフリーターという言葉があまり良くない働き方のような聞こえであった一方で、最近はフリーランスや個人事業主がかっこいい聞こえになっているように感じます。
もちろん1度しかない人生なのだから、
『自分が大事にしたいことは何なのか』
時間は限られているので、自分が納得できる生き方をするのが理想なのだと思う。
しかしながら、この「自分らしく」という意味合いについて『働き方』は慎重に考えた方が良いとも思う。
人にはいろいろなタイプがあるから、たとえば学校や会社という組織に『時間』や『仕事内容』を管理してもらう方がパフォーマンスが上がる人もいるだろうし、経理や事務作業等の細かいことが気にならないからこそ、タスクに集中できる人もいる。
何より、毎月一定額の収入が入ってくることが心の安定に繋がっていることも多い。
一方で、組織にいることでやりたいことを制限されることがストレスになる人や個人でする方が生産性が上がる人は、組織の一員として働くことはやっぱり向かないと思う。
就職氷河期世代を生き抜き同調圧力が染みついた世代の私にとっては、こういった働き方の選択肢が持てるような時代になってきたことは、本当にありがたい。
でも、染みついた昭和の価値観はそんなに簡単には変わらない。
『コツコツ頑張ればきっと大丈夫』
『真面目に一生懸命』
『根性と気合で乗り越えろ』
日本における多様性の浸透がじわじわと広がっているように感じるけど、拭いきれないこの昭和魂とどう向き合っていこう。