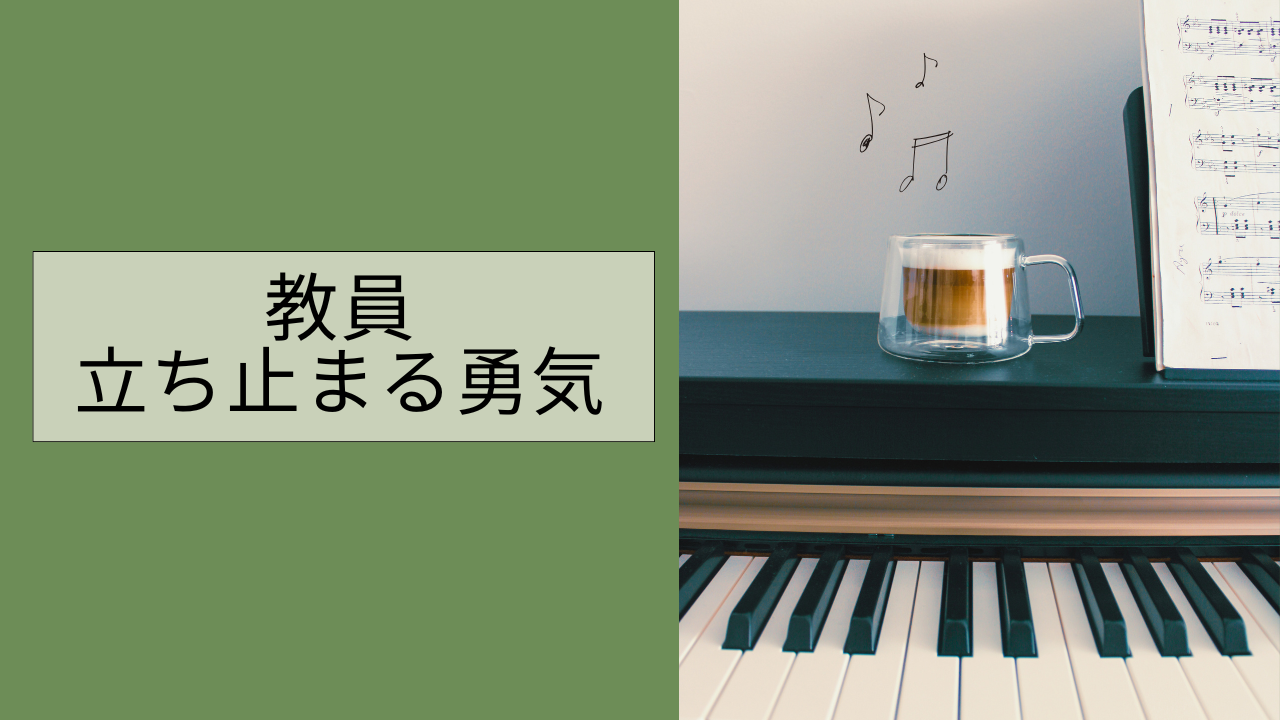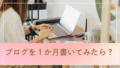最近、先生足りないとか
採用試験の倍率さがってるとか
よく耳にするなぁ
病気休職を取る先生も増えてきてるみたいやな。
過去最多の教員休職者数に驚かない理由
参考データ
2024年12月発表の文部科学省の調査によると、昨年度、うつ病などの精神疾患で休職した公立学校の教員は以下の通りです。
- 小学校:3443人
- 中学校:1705人
- 高校:966人
- 特別支援学校:928人
- 合計:7119人(前年度比+580人)
この数字は、1979年の統計開始以来、初めて7000人を超え、過去最多だそうです。病休取得後、約20パーセントの方が退職をされたそうです。
でも、この数字、学校現場にいると驚かないんです。私が長らく教員をしてきたからこそ、思うことがあります。
「私は大丈夫」—無理を重ねた先にあるもの
教員として働いていると、周囲には前向きで一生懸命な人が多く、「子どもたちのために」と頑張るのが当たり前の環境にあります。
私自身も長い間、無理をしすぎてきたのでは?ということに、最近になってようやく気がつきました。
「私がしんどくなるわけがない」
そう思い込み、病気で休む先生を横目に「私は大丈夫」と自分に言い聞かせながら、使命感と責任感だけで一年を乗り切る。
そして息つく間もなく新年度が始まる。それが教師。そんな日々の繰り返しです。
でも、あるときふと気づいたのです。
走り続けること、努力し続けること、いつも明るく元気でいること。
それが当たり前になりすぎて、自分の心と体が悲鳴を上げていることに気づかないまま過ごしていたのではないか、と。
そして、今まで「なぜ急に来られなくなるのだろう?」「けっきょく残されたメンバーがやらなあかんやん。」と思っていましたが、病休を取られる先生方の気持ちが、ようやく理解できるようになりました。
心が限界を迎えると、動けなくなってしまう。だから、病休は誰にでも起きることで、取得する人は悪くない。きっと真面目な先生だからこそ、取得した後に病休を取ったことでさらに苦しんでいる。
小学校は人手不足—ギリギリの現場
特に小学校は教員不足が深刻で、どこの学校もギリギリの状態で回っています。初めから余白のない人員配置ですから、そうなるのは目に見えていますよね。
「なんとか3月末まで不時着した」と思ったら、また4月が来る。教員はこの繰り返しです。
「人が足りないからこそ、頑張るしかない」
その気持ちも痛いほど分かるし、私自身もそうしてきました。でも、その結果、無理をし続けてしまい、気づいたときにはもう動けない、転職や自分の人生を考えることもできなくなるほど疲弊している、なんて、そんな悲しいことになってはいけないと思います。
だからこそ、立ち止まることが大切
心と体が悲鳴を上げる前に、
「今の自分の状態はどうか?」と立ち止まって考えることが大切ではないか、と思うのです。
もし、
「自分の身体が自分じゃないような感覚」になったら、病休という制度を使ったら良い!と思います。
病休は
「もうダメになった人が使うもの」ではなく、『自分』を取り戻すための制度です。
休むことで、心と体を回復させた上で、
- 「やっぱり教師を続けたいのか」
- 「それとも違う道を歩いていきたいのか」
を考える時間を持つことができます。
心と体が回復していない状態では、冷静な判断はできません。教員は公務員なので失業保険も受けられません。もし退職して次の仕事を探すとしても、健康な心と体がなければ、次の一歩を踏み出すことさえ難しくなってしまいます。
自分を大切にすることは、子どもたちのためにもなる
「自分がしんどくなるわけがない」
「私が頑張ればなんとかなる」
そう思って走り続けてきた私ですが、今はこう思っています。
「先生自身が元気でいることが、子どもたちのためになる」
自分を大切にすることは、決して甘えではありません。心と体が元気だからこそ、子どもたちの前で笑顔でいられるし、良い授業もできる。
もし、少しでも「しんどい」と感じたら、どうか無理をしすぎず、立ち止まることを考えてみてください。
病休を取ることも選択肢のひとつ。
それは「逃げ」ではなく、「自分を取り戻すための時間」なのです。
以上、ここまで読んでくださりありがとうございます。
先生の前にあなた自身の人生が豊かで楽しくなることを願って。