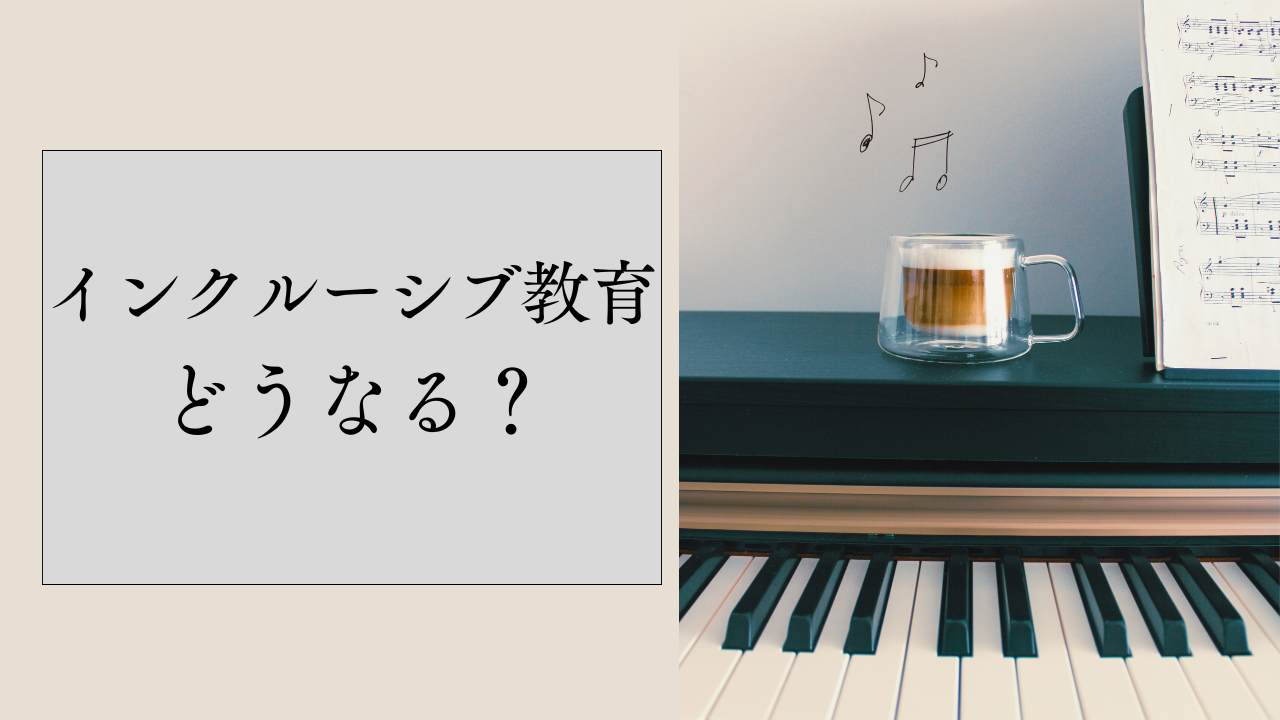窓際のトットちゃんのアニメ観たら
涙が出たわ。
日本の学校、何やってるんやろって。
私はトモエ学園の先生みたいに、子どもを心底、信じられてたかな。
小説で長年愛され続けている『窓際のトットちゃん』
何年経っても、世界中で読み続けられる名作です。
Netflixで映画版が2024年12月8日からスタートしていますが、
窓際のトットちゃんが学ぶトモエ学園に、
今、まさに日本の教育が転換期として向き合おうとしている
『インクルーシブ教育』の原点をみているように感じています。
今、日本の公教育が目指している
『子どもの主体性』
『子ども同士の学び合い』
『子どもの自由な学びに合わせた自由進度学習』
『障害のある子もない子もともに学ぶ』
すべてが、トモエ学園の日常に入っている。
文部科学省のHPにインクルーシブ教育とは
同じ場で共に学ぶことを追求する、(途中抜粋)
個別の教育的ニーズのある児童に対してその時点で最も的確に応える指導を提供できる、多様で柔軟な仕組みを整備すること
と記されているが、
なぜ、戦前の日本教育の中でトモエ学園が
普通にできていたことが、
今、新たに構築されていかなければいけないことになったのか。
それは、まさに日本の教育の
『みんな同じであること』
を美化してきた蓄積であるようにしか見える。
『みんな同じであること』
を求めた反対側に
みんなと同じにできなくて、つらい思いをしたり、学校に行かない選択をしたり、追い詰められた親や子どもがいるように思う。
今、日本の教育は
一斉指導の限界にきている。集団教育がどの学校でも難しい現状がある。
終身雇用もほぼ崩壊し、良い大学から一流会社の構図は成立しなくなり
生き方や働き方に多様性を求める大人の世界に、
学校教育は昭和時代の
『みんな同じであること』
をまだ美化し続けているように見える。
トットちゃんは、いわゆる普通の公立学校では、問題児で何をしても怒られ続けて退学になったけど
トモエ学園の先生は、何をしても、トットちゃんを見守る。
学校を変わったトットちゃんの表情から、
不登校や特別支援の子どもたちがが増える理由を
考えさせられる。
変わるのは、子どもではない。
子どもが心の底から生きていることを楽しみ、
あらゆる不思議に体当たりでぶつかっていく。
トットちゃんが出会った、
危なっかしくても子どもを信じて待てる
トモエ学園の先生のように
口出ししたくても信じて見守り続けられる
トットちゃんのお父さんやお母さんのように
そんな風な大人でありたいと強く思う。
多様な学び方があたりまえになること、
日本のインクルーシブ教育に必要なことは、
そんな大人たちの優しさや温かさ、
そして子どもを信じる『覚悟』なんだと思う。