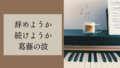令和7年3月で、定年まで待てずセミリタイアすることになりました。定年まで働くつもりをしていましたし、退職金は2,000万円いただけることを夢見ていましたが、大きな決断をすることとなりました。
今までも、辞めたいやめたい、と何度も思っていましたが実際に踏み切れなかった私が『退職』を決めた5つの大きな理由をご紹介します。
1 定年までの見通しがついてしまった。
毎年、どこの学校に配属されるかわからないし、受け持つ学年、校務分掌だってわからない。出会う先生も、子どもも、保護者の方も、もちろん違うんだけど、
なんとなく、60歳の定年までのあと10年きっとこんな感じなんだろうな、と自分の過ごし方や仕事に対する気持ちの『見通し』がついてしまいました。
教員の1年の流れにも、自分の中でマンネリ化が出てきていたように思います。行事が合って、会議が合って、何かしらテーマを決めて研究をして。
それと同時に、先が見えてしまったことが、私にとっては
『このままで人生終わっていいの?』
『これが本当にやりたかったこと?』と自分への問いかけを濃くするものでした。
若いころは、クラスもまともにまとめられないし、授業も見せられたものじゃなかったし
ただ、がむしゃらに、
『どうやったらクラス全員の子どもたちが楽しく九九が覚えられるだろう。』
『お楽しみ会でどんなことをしたらもっとみんなが仲良くなれるだろう。』と
ワクワクしながら仕事ができていたような気がしますが、【子どもが大好き!】の気持ちは変わらず、でも、きっと10年こんな感じで続くんだろうな、と思ってしまったことが大きな1つめの理由です。
2 体力的にしんどい
いわゆるアラフォーまでは、しんどいしんどい、と言いながらも
寝不足でも何とかなったし、栄養ドリンク飲んだら遅くまで職員室で楽しく頑張れたんですけど
50歳を迎えるあたりから、
寝てもちゃんとしんどい笑
朝は元気でも16時ごろになるとクタクタになる
大好きだった夏のプール授業が嫌で仕方なくなる
寒い運動場でのマラソン授業が堪える
月曜日から金曜日まで毎日元気に、そして笑顔で、頑張ることが体力的にも精神的にもしんどくなってきたんです。
定年まで教員を続けられた方々を心から尊敬しますし、本当にすごいこと!なんだとこの歳になって改めて痛感しています。
3 周りに病気や別れが多くなった
50歳も近くなると、親世代で小さいころから可愛がってくださっていた方やお世話になった恩師の先生など、どうしても順番だから仕方ないことなのですが、別れが多くなってきました。
それと、私も人間ドックに毎年行っていますが
『今年の人間ドックで引っかかってん。』というお友だちが、急に体調が悪くなり亡くなられたり
『腫瘍が見つかって。』と大きな手術をするお友だちがいたり。
この病気のお知らせや人の別れに出会ったとき、
『今を大切に生きよう。』と強く思うようになっていきました。慌ただしくがむしゃらに毎日を走っていて良いのか疑問に思うようにもなりました。
そして、もし、明日私がこの世からいなくなるとしたら、
胸を張って『今日も先生でいたい!』と思うかな、自問自答するようになり
その答えがノーになりました。
4 段取りばかり考える毎日が嫌になった。
教師の仕事は、段取りがものすごく大事だと思っていて
いつも、
明日の授業はどうしよう。
来週の行事に向けてこれはしておかないと。
このプリントは金曜日に返して。
今日の頑張りは次の通信に載せて。
と段取りばかり考えながら仕事をしていました。
プライベートでも、
帰ったらまず洗濯機まわしてから晩ごはんつくって。
子どもの書類は明日までに書かないと。
歯医者の予約を入れないと。
銀行に行くタイミングは来週の出張の合間に。
と、頭の中は『やることリスト』でいつもいっぱい
あれして、これして、それして・・・
慌ただしく生きる方が自分の性に合っていると思っていたけど
自分のやりたいこと生きたい生き方って本当にこうなのかなと思ったときに
一旦、立ち止まろう、と思いました。
5 チャレンジしたかった
これがやっぱり1番大きな理由
教員として頑張ってこれた、楽しいこともいっぱいあった、給料も年々上がってくるし安定もしてる
でも、
自分の可能性ってまだあるんじゃないか
公務員だとできることが限られてるから
何かやってみたいと思ったときに制限が多いから
思い切って守備能力を持たずして
自分が社会で通用するか、試してみたかった
以上が私が定年を待たずに早期退職を決めた5つの理由です。
読んでくださった方の何かしらの参考になれば嬉しいです。ここまで読んでくださり、ありがとうございました。