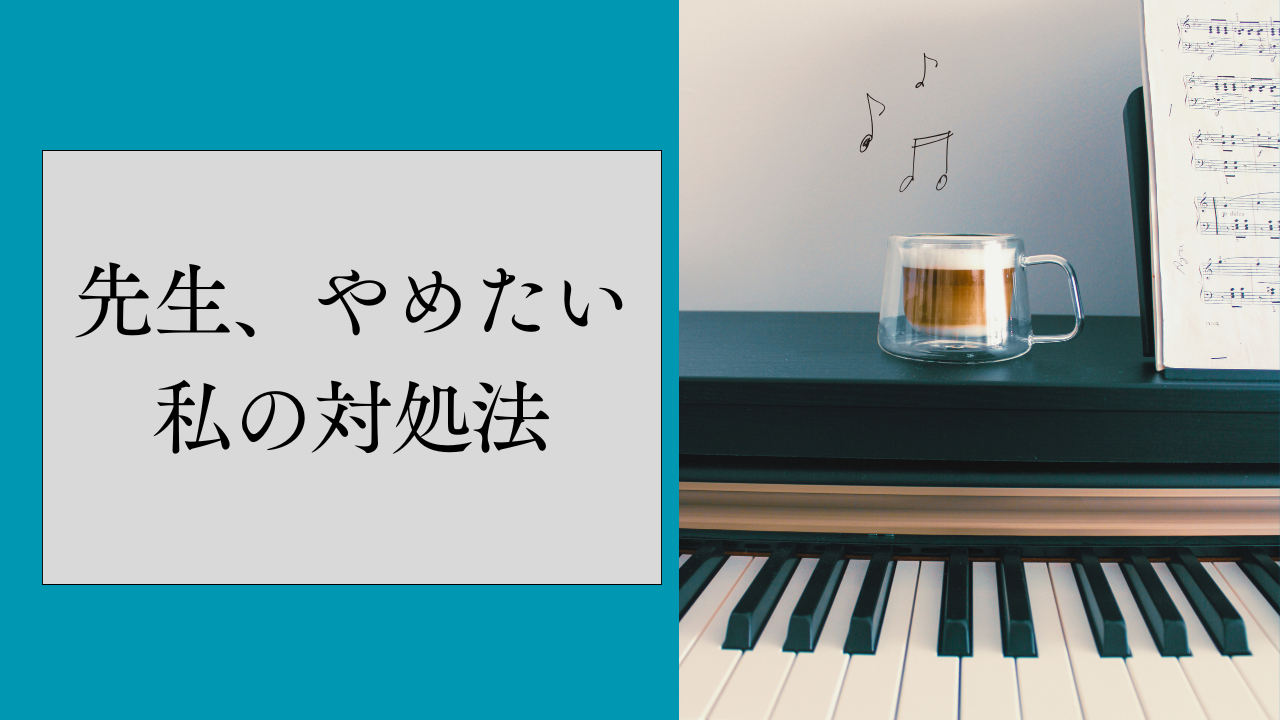先生だって、しんどくなるで。
だって、先生の前に
当たり前やけど、私は私、あなたはあなたやもんな。
20年以上、教員として子どもたちと向き合ってきました。でも、その道のりは決して平坦なものではありませんでした。
何度も、
- 「もう、教員を辞めたい」
- 「先生なんて続けられない」
- 「こんな仕事、もう嫌だ!」
そんなふうに心がポキッと折れる音がして、体ではなく心が悲鳴をあげることがありました。
理由はそのときどきで違いましたが、何度か「もう限界かもしれない」と感じることがあったのです。
もちろん、自分の人生なので、自分で決めて動けばいい。でも、目の前には子どもたちがいて、保護者の方々がいて、一緒に頑張る仲間がいる。そんな状況では、簡単に投げ出せませんでした。
そんな私が、心が悲鳴を上げたときにしていたことをご紹介します。
1. 同期に話す
「そんなこと?」と思われるかもしれませんが、私は同じ学校の先生には相談しにくかったのです。
確かに、同じ学校の先生は現状をよく理解しているので、解決策を一緒に考えてくれるかもしれません。でも、心が本当にしんどいときは、そもそも改善策を考える余裕すらないことがあります。
- 「こうしたらうまくいくんじゃない?」
- 「次の会議で私が意見を言ってあげようか?」
そんな言葉が、かえって自分を追い込んでしまうこともあるのです。
だからこそ、私は「学校」「先生」という価値観を共有できる同期に、ただ話を聞いてもらうようにしていました。同期なら押し付けられることも、責められることもない。振り返れば、話すことで心が軽くなっていたのだと思います。
2. とりあえず1日休む

心がしんどいときは、いくつものストレスが重なって、心のコップがあふれそうになっている状態です。
学校では、一度出勤してしまうと、時間が止まることはありません。授業、会議、子どもたち、保護者対応……。
「ぼーっとできる時間は1㎜もない」
「まったくドラマ(トラブル)がない日はない」
そんな環境のなかで、心がいっぱいになったときには、1日だけ年休を取って、逃げることを選びました。
もちろん、頻繁に使ったわけではありません。でも、2~3年に1回くらい、この「1日逃げる」という方法をとったおかげで、20年以上続けられたのかもしれません。
3. 本を読む
優しい言葉をかけられても、話したくないくらい心が疲れているときがありました。
- 「話、いつでも聞くよ」
- 「相談のるから校長室においで」
- 「気分転換にご飯でも行かない?」
どれもありがたいのですが、そんなときは誰とも話したくない。泣いてしまいそうで、愚痴をこぼしてしまいそうで、そんな自分が嫌になりそうで。
そんなとき、私は一人で本を読みました。
活字を追うことで心が無心になり、新しい情報を入れることで余計なことを考えずに済む。私にとって「本を読む」ことは、心がしんどいときの処方箋のようなものでした。

特に、一番救われた本が、
カマタクさんの『おまえのために生きていないので大丈夫です。』
この本を読むと、「まぁ、いっか」と思えるようになり、元気が出てきます。
先生も「自分」を大切にしていい
最近、病休に入る先生が年々増えていると聞きます。その影響で、担任の先生が不足し、学校内の先生の数も足りていない。特に小学校では、これが死活問題になっています。
私は20年以上、教員を続けてきましたが、どの先生も真面目で一生懸命。でも、先生だって、先生になる前は「一人の自分」です。
「自分が自分じゃなくなるくらい頑張らないといけない仕事」
それは、もはや仕事ではないのではないでしょうか。
以上、私が教員として心がしんどいときにしていた対処法をご紹介しました。明日が、今日より少しでも明るく楽しい1日になりますように。